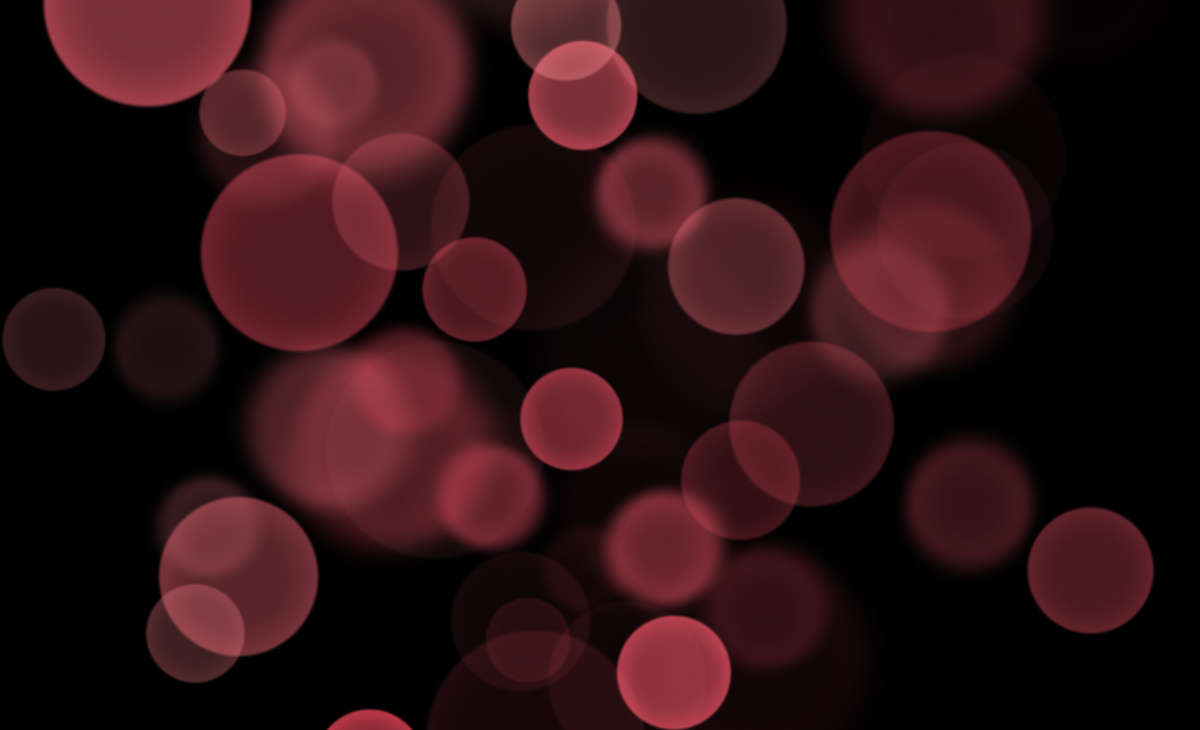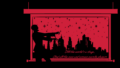怖い話「炭酸」
私は美咲という名の女性を知っていた。彼女は都会の喧騒に疲れ切り、その孤独な夜を癒すため、炭酸水に依存するようになっていた。シュワシュワとした冷たい泡が喉を通る瞬間、彼女はほんの一瞬だけ、この現実の冷たさから逃れられるような気がしていた。
ある蒸し暑い夏の日、美咲はいつものスーパーで見慣れない炭酸水のボトルを見つけた。ラベルには何か古めかしい文字がかすかに読めるだけで、製造元も不明だったが、妙に惹かれるものがあり、彼女はそれを買った。
その夜、彼女は早速その炭酸水を開け、グラスに注いだ。泡が立ち昇る様子はどこか異様で、まるでグラスの中で何かが蠢いているように見えた。しかし、美咲はその異常に気づかないふりをし、炭酸水を口に含んだ。
飲んだ瞬間、美咲は奇妙な感覚に襲われた。泡が喉を通るたびに、冷たい恐怖が全身を走り抜け、体の内部で何かがざわめき始めたのだ。その感覚は、まるで無数の小さな生き物が喉から体内へ侵入し、彼女の肉体を内側から侵食しているかのようだった。
夜、彼女は悪夢を見た。暗闇の中、彼女は自分の家に立ちすくんでいた。家中が不気味な静寂に包まれ、唯一聞こえるのは微かな泡の音だった。音の出所を探し求めると、キッチンのテーブルに置かれたグラスが視界に入った。グラスの中の泡は、まるで生きているかのように異様な動きをしており、グラスの縁を越えて這い出し、床に広がり始めた。
泡は床を這い進み、美咲の足元に到達した。泡が彼女の肌に触れた瞬間、冷たく不快な感覚が彼女を貫き、足が動かなくなった。そして、泡は次第に彼女の全身を覆い尽くし、彼女の体を締めつけ、息苦しさが襲ってきた。
目が覚めた時、美咲は自分が冷たい汗でびっしょり濡れているのに気づいた。夢から覚めたにもかかわらず、喉の奥に残る泡の感触が消えず、恐怖は彼女の心を締め付け続けた。
次の日、美咲は再びその炭酸水を口にしたが、その瞬間から彼女の体に異変が起こり始めた。皮膚の下で何かが蠢いている感覚が強まり、体が軽く震え始めた。鏡を覗き込むと、彼女の肌は青白く変色し、目の下には黒い影が浮かび上がっていた。彼女は自分の体が何か得体の知れないものに支配されているように感じた。
数日後、彼女は仕事を欠勤し、同僚たちも連絡がつかなくなった。心配した友人が彼女の家を訪れると、家の中は不気味な静寂に包まれていた。キッチンには空のグラスが置かれ、そのグラスの底にはわずかに泡が残っていた。
美咲の姿はその後、誰にも見られていない。彼女の家に残された炭酸水のボトルは謎のまま消え失せ、冷蔵庫も空っぽだった。唯一残されたのは、キッチンに置かれたグラスの底で、今でも微かに泡が弾ける音が響いているという、冷たい恐怖の記憶だけである。
人々はその家に近づくことを避けるようになり、夜になると誰もがキッチンから聞こえる泡の音に耳を塞いだ。それは、美咲が体験した異様な出来事が、単なる悪夢ではなく、何か深淵の力が関与していたことを暗示しているかのようだった。